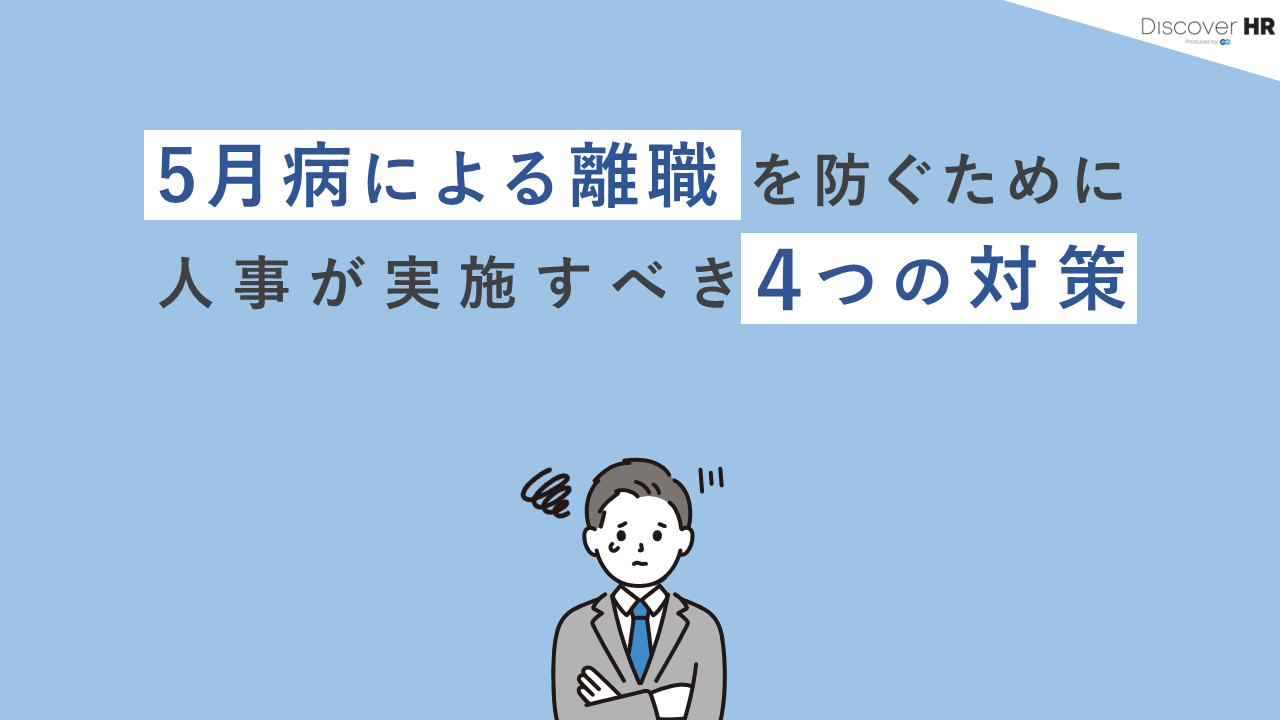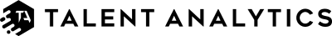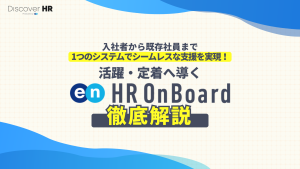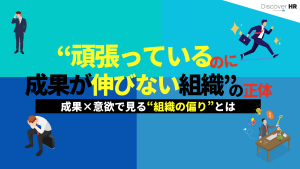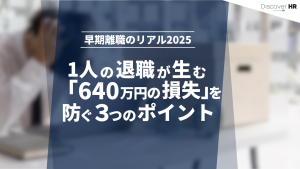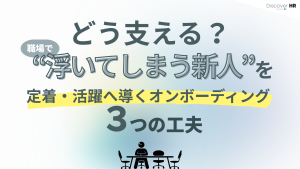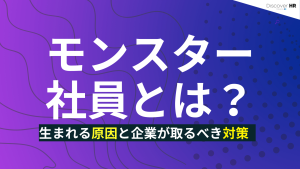5月は新しい環境に慣れる時期である同時に、ストレスがピークに達することから「5月病」と呼ばれる症状が出やすくなります。そのため、離職率が上昇する時期でもあると言われます。そこで今回は、この5月病を防ぐために人事ができる対策を4つご紹介します。ぜひお役立てください。
5月病の症状とは
・疲れやだるさ
・ストレスやイライラ感の増加
・集中力やモチベーションの低下
・睡眠障害や不眠症の悪化
・身体的な不調、頭痛や肩こりなど
5月病は正式な病名ではありませんが、疲れやストレスからうつ病や適応障害などの精神的な問題を引き起こす可能性があります。症状を見過ごすことで、社員の業務生産性が低下することはもちろん、休職や退職を引き起こすリスクがあります。
5月病による離職を防ぐ4つの対策
5月病が原因で発生する離職を防ぐには、労働条件の改善やストレス解消法の取り入れなど、予防的な取り組みが重要です。
1. ストレス原因の特定
ストレスの原因を特定することは、適切な対策を講じるために非常に重要です。ただし、ストレスチェックなどの結果をただ見るだけではなく、上司や人事担当者が実際に対策を講じることが大切です。
例)
・アンケート調査
∟全社員対象にアンケートを実施し、ストレス原因や解消策を聞き出せます。
・ストレスチェック
∟社員のストレスを早期発見し、適切な対策を講じることができます。
・1on1面談
∟上司が部下に話を聞くことで、より細かいストレス原因を把握できます。
2. コミュニケーションの促進
社員同士のコミュニケーションを促進することは、ストレスの発散や解決策の発見にもつながります。そうすることで、職場の雰囲気が改善され、ネガティブな連鎖による離職を防ぐことにつながります。
例)
・社内イベント
∟社員同士の交流機会を設けることでコミュニケーションを促進できます。
・チームビルディング
∟チームビルディングを通じて、チームワークや協調性を高めることができます。
・フィードバック
∟上司から部下へ評価を行うことで、部下は成長の方向性を把握できます。
3.福利厚生の充実
福利厚生を充実させることは、社員の健康管理やストレスケアには大切な要素です。その他にも、子育て支援制度の導入や育児休業の取得を促すなど、社員が安心して働ける環境づくりが求められます。
例)
・健康診断の実施
∟健康状態を定期的にチェックし、早期発見や予防につなげることができます。
・メンタルヘルスサポート
∟専門家による心理カウンセリングやストレスケアなどを提供します。
・リフレッシュスペース
∟読書や運動スペースを設置することで、ストレス解消につなげることができます。
4.ワークライフバランスの改善
仕事とプライベートを両立させることで、ストレス解消やリフレッシュ、日々の生産性向上につながります。
例)
・フレックスタイム導入
∟勤務時間を調整できるようにすることで、プライベートの時間を確保できます。
・在宅勤務の推奨
∟通勤時間の削減や自宅での仕事環境の改善につながります。
・オンライン教育の充実
∟社員が自己研鑽に励み、ワークライフバランスを改善することができます。
さいごに
5月病を原因とする離職を防ぐために、人事は社員の心のケアに注力する必要があります。コミュニケーションの促進やリラックスできる空間の整備、ストレスチェックなどメンタルヘルス対策の徹底など、多岐にわたるアプローチが必要です。これらの取り組みを通じて社員の心身の健康をサポートし、離職防止につなげましょう。