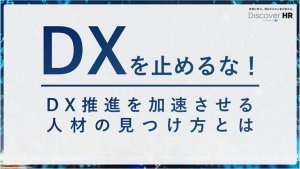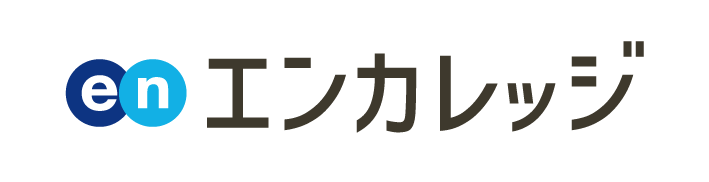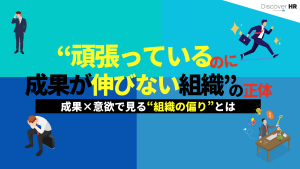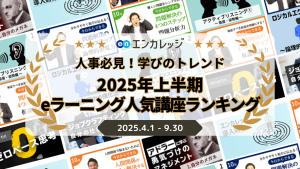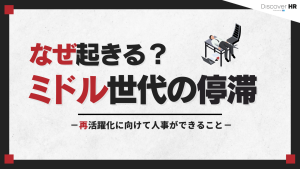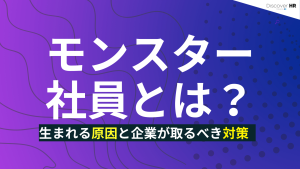日本の最北端、宗谷地方に位置する北海道 中頓別町(なかとんべつちょう)。
住民の暮らしを支える「中頓別町役場」では、業務の複雑化と職員数の減少、そして加速する行政DXへの対応という三重の課題に直面していました。この難題に立ち向かうべく、町長よりDX推進の任を受けた市本様と白井様に、人材育成の取り組みについてお話を伺いました。
なぜDX推進に向けて「人材育成」を重視されたのですか?
中頓別町では、若年層の流出や担い手不足といった課題が、町の持続可能性に大きく影響しています。
これらの課題は、今や多くの地方自治体が直面している問題であり、特に小さな自治体にとっては特に深刻な問題とも言えます。こうした課題を抱える中、中頓別町は、次世代を担う若手の育成や、地域の未来を見据えた取り組みを先んじて進めてきました。
そんな中、社会の流れや変化に伴い「中頓別町役場」を取り巻く環境も大きく変化してきました。
業務の複雑化・高度化が進み、限られた職員で多様な業務をこなす必要がある中、DX(デジタルトランスフォーメーション)や行政手続きの電子化も急速に求められており、職員には、これまで以上に高いデジタルリテラシーが求められるようになってきたのです。
人材育成の面で課題視したことは2つありました。
1つ目は、町役場内で広がる「デジタルデバイド(情報格差)」の存在です。
優秀かつ意欲的に学んでいる職員もいる一方で、PCの基本操作に不安のある職員も少なからずいました。一部の人だけがどんどんスキルを伸ばしていく中、学ぶ機会を得られず取り残されてしまう人が出てくる——それが、組織全体の成長にブレーキをかけているように感じたのです。
また2つ目に、個人的に強く感じていたのが、DXの本質は年齢や立場に関係なく重要ということです。
DXとは、単にITツールを使いこなすことではなく、デジタルの力を活用して目の前の課題に対してどれだけ思考を深められるか、筋の良いアイデアを出せるか——そうした力が問われていると考えています。
そう考えると、DX人材育成というのは若者に限った話ではなく、むしろベテラン職員の豊富な経験や知見にこそ、DXを実装する際の「勘どころ」が眠っているとも言えます。そんな考えから年齢や立場に関係なく、誰もがその力を磨き続けられる仕組みが必要だと感じていました。
eラーニング「エンカレッジ」の導入背景と、
初年度の状況を教えてください。
こうした問題意識のもと導入したのが、eラーニングシステム「エンカレッジ」でした。
このシステムの魅力は、時間や場所にとらわれず、自分のペースで学べる点にあります。ITやDXに関する講座だけでなく、「論理的思考力」や「問題解決力」など、実務に直結する内容も豊富にそろっており、職員のスキルアップを幅広く支援できます。また、行政機関に特化した専門的な講座が中心ではないことから、堅苦しすぎず、空いた時間で気軽に取り組める点も評価し、導入に至りました。

導入初年度は、現場への周知や仕組み化を行った結果、98%という高い受講率を記録しました。
しかし一方で、導入当初ならではの苦労もありました。ある日、講座を“流し見”している職員を見かけ、「なぜ?」と尋ねると「毎月3講座が必須だから…」との返答。意図していた「学び」とはズレていたことに気づき、私たちの思いや危機感がうまく伝わっていなかったと反省しました。
そこからは、受講の必要性を説いてみたり、受講できない要因をヒアリングしてみたりと奮闘する日々が続きました。また、受講後に寄せられる感想や意見に対し、上司が十分に対応できるスキルや余力を持ち合わせていないといった新たな課題も見えてきました。
それでも、危機感を持つ職員が自ら積極的に多くの講座を受講し、特に「問題解決力」などの講座は人気を集めました。仕事が煮詰まったときの“リフレッシュ”として活用する声もあり、私たちの意図が届いた実感が得られた瞬間でもありました。
また、想定外だったのが、就職説明会での学生からの好反応です。最近の若い世代は「入社後にどれだけ成長できるか」を重視する傾向が強く、こうした学習環境の整備は「前向きに学び続けられる職場」として評価されているようです。
今後の展望をお聞かせください 。
今後は、講座受講後に提出される「アイデアシート(KAIZENシート)」を起点に、上司と部下が対話できる仕組みをつくっていきたいと考えています。最初は感想を言い合うだけでも構いません。新しい知識をインプットし、それをもとに意見を交わし、職場全体でアイデアを生み出していく——そんな文化を根付かせたいと思っています。

また、現在、DX関連のツールは徐々に整いつつありますが、まだ活用できる職員は限られています。エンカレッジの活用を通して、ひとりひとりがツールを使いこなせるようにしていくことで、現在業務にかかっているコストや時間の削減につながるのではないかと考えています。そして、空いたキャパシティを、住民の幸せを考える時間へとつなげていきたいと考えています。

「限られた人員で、いかに住民の幸せにつながる仕事をしていくか」
——そんな問いに真剣に向き合う市本様と白井様の姿勢が印象的でした。
DXはツール導入がゴールではなく、それを“使いこなせる人”を育て、現場に根づかせていく地道なプロセスがあってこそ。年齢や経験に関係なく学び合い、考え合う風土づくりに挑戦する姿からは、多くの自治体に通じるヒントが見えてきます。
小さな町から生まれる大きな変化に、今後も注目していきたいと思います。
関連サービス
エンの取り組み

社会的なインパクトが特に大きい人材採用「ソーシャルインパクト採用」を支援するプロジェクト。中央省庁の幹部候補、自治体の副市長やDX担当、NGO/NPO・スポーツ団体・志ある企業の中核メンバーなど、様々な採用をエン全社を挙げて支援しています。
▶自治体のプロジェクト一覧はコチラ
あわせて読みたい