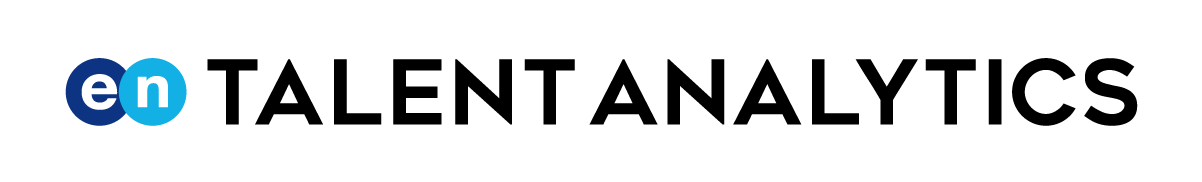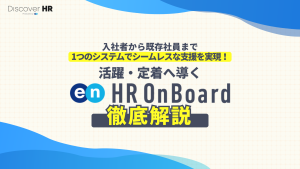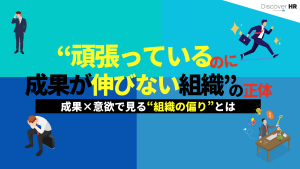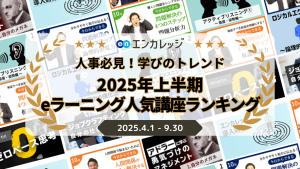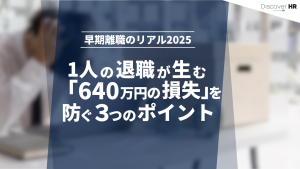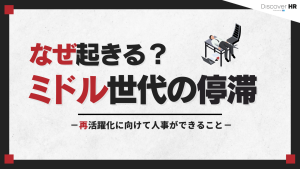昨今、組織の中では、高い成果を出す一方で、周囲のメンバーを疲弊させてしまう“優秀だけど嫌な人”──いわゆる「ブリリアントジャーク」が、経営や人事の間で広く警戒されるようになっています。
彼らは短期的には成果を出してくれる存在であるものの、心理的安全性の低下、長期的にはチームの停滞、離職率の上昇といった深刻な影響を及ぼすことがあります。
本コラムでは、ブリリアントジャークの特徴と、その傾向を強めうる認知バイアスを整理し、組織で“生まない・増やさない”ために人事・管理職が実践できる具体策をご紹介します。
ブリリアントジャークとは何か
定義
「ブリリアントジャーク(Brilliant Jerk)」とは、
「優秀ではあるものの、周囲に悪影響をもたらす人」を指す概念です。
特徴
用語が広まった背景
この概念は、Netflixの企業文化がきっかけで広く知られるようになりました。同社の採用サイトでは「どれほど優秀な人材であっても、同僚に礼儀正しく、敬意を払えない人は私たちの組織には要らない」と明言しており、協働を重視する文化を競争力の源泉と考える姿勢を示しています。
組織へ及ぼす悪影響
スキルや業績だけを見れば優秀である一方で、横柄な態度や協働を阻害する振る舞いによって、組織における生産性を低下させる懸念が考えられます。
認知心理学から見る、ブリリアントジャークを引き起こす3つのバイアス
ブリリアントジャークは生まれつきの性格だけでなく、本人と組織環境の相互作用によって後天的に強まっていく場合があります。過去の経験や環境などにより、「認知の偏り」が強まり、本人が意識しないまま特定の思考パターンに陥っている可能性があるのです。この認知の偏りには、次のようなケースが挙げられます。
「自己中心性バイアス」
【定義】
自分の視点を基準に物事を捉え、他者の事情や背景を想像しづらくなる傾向
【職場での例】
相手も知っているだろうと考え、前提説明を省く
相手の置かれている状況や負担を確認せず、厳しいフィードバックをする
「自己奉仕バイアス」
【定義】
成功は自分の能力、失敗は外部要因のせいと捉える傾向
【職場での例】
成果は自分の手柄として強調し、ミスは周囲のせいにする
フィードバックを素直に受け入れず、しばしば反論する
「確証バイアス」
【定義】
自分にとって都合の良い情報ばかりを集め、反証する情報を無視する傾向
【職場での例】
苦手な相手のミスだけに注目し「やはり使えない」と結論づける
チームメイトの意見を聞かず「自分が正しい」という確信を深める
バイアスは誰にでも起こりうる認知の習慣であり、人事や管理職の適切な介入によって改善できる余地があります。
ブリリアントジャークを生まない・増やさないための対応策5選
① 失敗事例の共有を称賛する
失敗談の共有は組織の学習にとって大きな財産ですが、減点を恐れて避けられがちです。管理職が「その共有はチームの資産だ」と価値づけすることで、失敗を“学習リソース”として捉える文化をつくることができます。管理職自身が小さな失敗を率先して開示すると、メンバーも安心して共有しやすくなり、心理的安全性の向上にもつながります。
② 評価の基準に「弱みの改善」「利他性」を組み込む
評価項目に、利他性や弱みの改善努力といった視点を入れることで、組織が大切にする行動を明確に示すメッセージになります。これにより、個人成果(利己性)だけでなく、他者貢献(利他性)のバランスを社員に促すことができます。
③ ピアボーナス・サンクスカード制度を導入する
感謝や称賛は、意識していないと行動に移せないことも多いものです。制度として仕組み化することで行動が促され、また「称賛される行動」をメンバー同士で学び合う効果(観察学習)も期待できます。
④ 会議などの場で「他者紹介」を取り入れる
他者紹介のためには、相手の強みや日々の貢献に自然と目を向ける必要があります。このプロセス自体が、お互いへの尊重を育むきっかけになります。また、紹介される側にとっても、自分の価値を再確認できるポジティブな体験になります。
⑤ 健全な衝突を促す仕組みをつくる(反対意見+代替案)
批判だけの意見を防ぎ、“評論家”ではなく“当事者”として議論に参加する姿勢を促します。代替案を考える過程では、相手の意見の背景を理解する思考習慣も育まれます。「反対 → 代替案 → 組織にとってのメリット」というフレームを提示したり、管理職が問いかけながら代替案を引き出したりすることも有効です。
まとめ
ブリリアントジャークを放置すると、心理的安全性の低下や、組織の停滞といった深刻な問題につながる可能性があります。成果と協働が両立する組織をつくるには、個人のスキルだけでなく、文化や仕組みの見直しが欠かせません。本コラムの内容が、日々のマネジメントや組織づくりを考える際のヒントになれば幸いです。
エンで支援できること
エンでは、採用時の見極めから入社後の育成・マネジメントまで幅広く活用できる適性検査「Talent Analytics」をご提供しています。また、採用・育成・定着に役立つテーマで各種セミナーも開催しています。