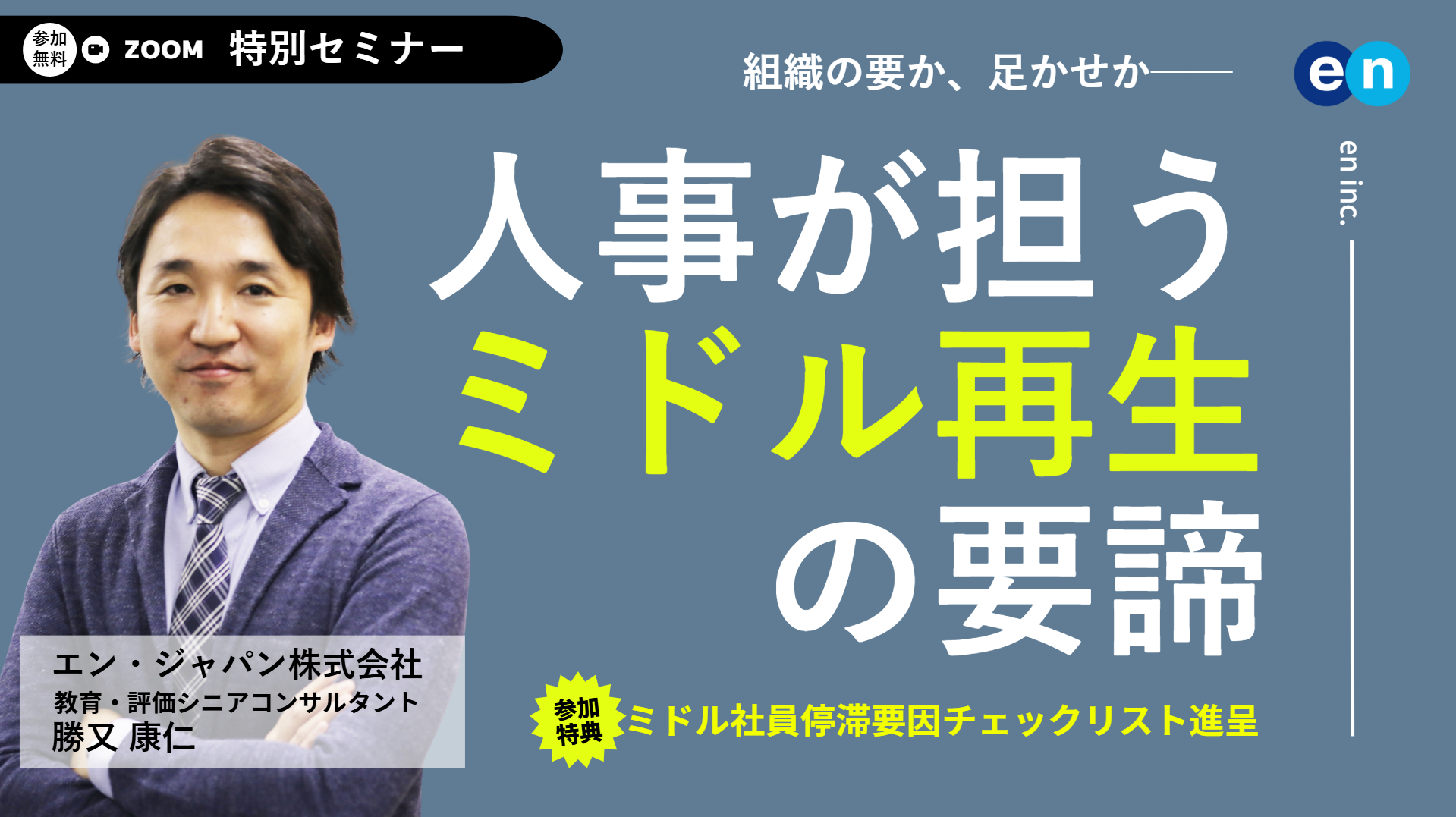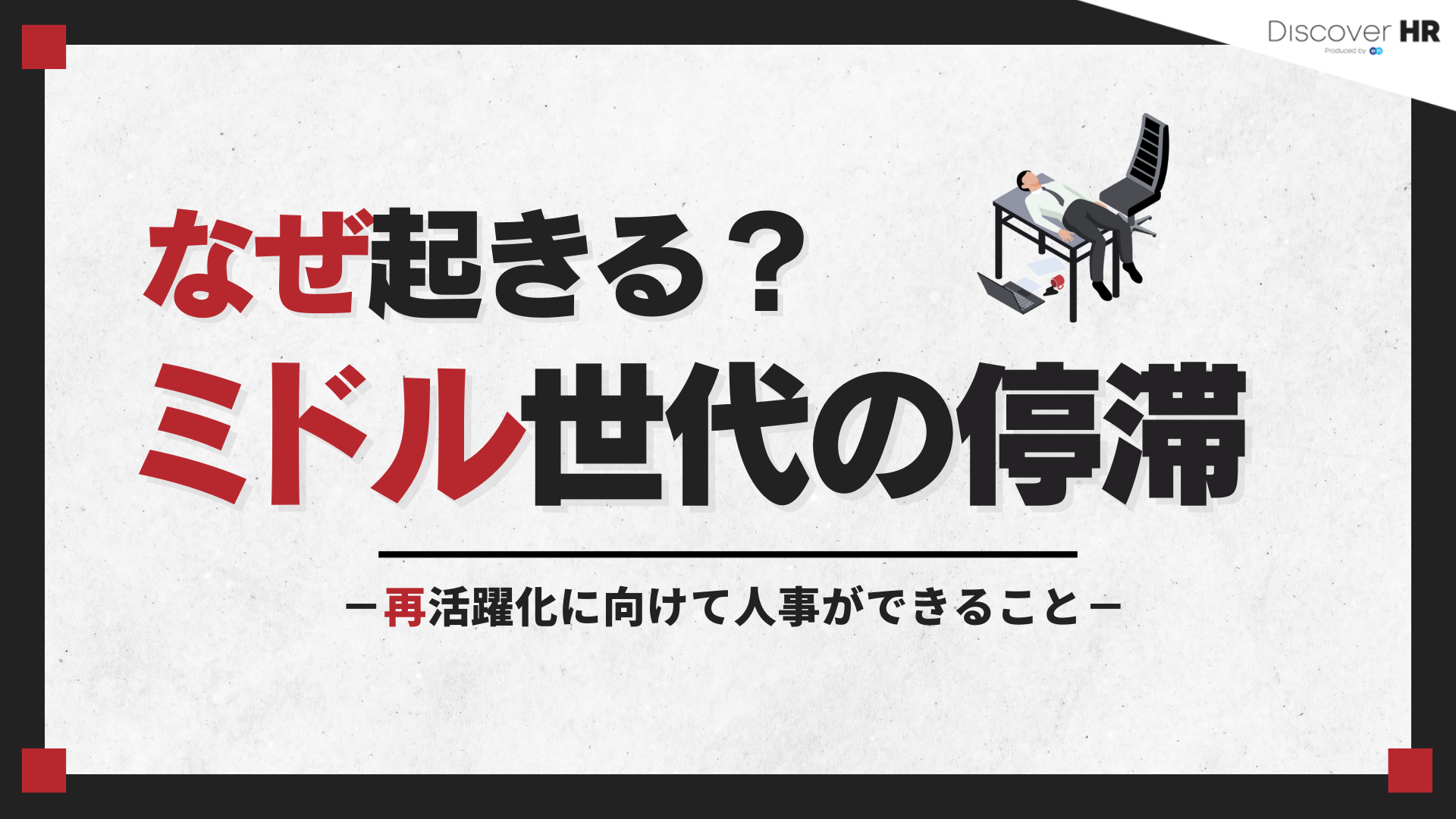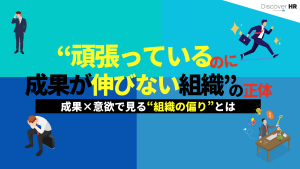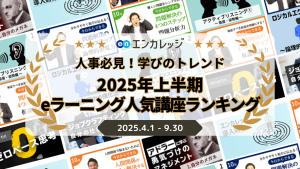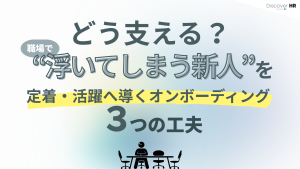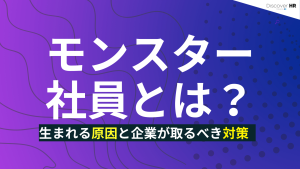組織の中核を担うミドル社員(一般的には、35歳~50歳の層を指すことが多い)。
ミドル社員は豊富な経験や知見を持ち、本来なら事業を推進する大きな力となる存在です。
ところが近年、「社会人としてできるだけ長く働き続けたい 」と考える人は多い一方で、現場では停滞感を抱えているミドル世代が増えていると言われています。
本コラムでは、なぜ今ミドル世代に注目が集まるのか、その背景と停滞要因、そして活躍化のポイントをご紹介します。
なぜ今、ミドル世代に注目が集まるのか
人口・労働力構造の変化
少子高齢化が進み、若手人材の絶対数は減少しています。
その一方で40~50代の就業者は増え続け、いまや社会全体の生産性維持・成長の鍵を握る層になっています。
定年・就業期間の長期化
「高年齢者雇用安定法」の改正により、65歳や70歳までの雇用確保措置が求められるようになりました。キャリア後半のあり方は、個人の問題にとどまらず、企業の競争力を大きく左右するテーマになっています。
転職の流動性と意欲の高さ
2025年4月に公開されたエンの調査でも、ミドル世代の転職者数は2018年比で約2.5倍に増加しています。その中でも特に50代は5倍以上と、顕著な伸びを見せています。
「今の会社でこのまま過ごすのか」「別の環境で挑戦するのか」―ミドル社員の選択は企業にとって人材流出リスクにも直結します。
活躍か、停滞か。―企業にとってのチャンスとリスク
ミドル世代を活躍に導くことで、事業や組織に大きなチャンスを生み出せます。一方で、停滞が続いてしまうことで、組織における深刻なリスクにつながる懸念もあります。
チャンス
リスク
停滞を生む要因とは?
多くの場合、停滞は個人の意欲だけでなく、組織や環境との関係性から生まれています。中でも大きく分けて3つの要因に整理することができます。
役割・スキルのミスマッチ
これまでの経験が活かせない業務や、逆に新しいスキルが求められる環境に適応できず、自信を失ってしまいます。
モチベーション・キャリア展望の課題
マネジメントポジションの頭打ちやキャリア後半の見通しがつけづらいことで、業務や組織に対するエンゲージメントの低下をもたらします。
組織・上司との関係性の課題
若手とのジェネレーションギャップや、上司との板挟みなどにより孤立を感じやすくなると言われています。
こうした要因が積み重なると、「変化を避けたい」「現状を維持したい」という心理が強まり、結果として停滞感につながります。
ミドルを活躍させるための4つのポイント
停滞を解消し、活躍してもらいやすくするためには、次の4つの方向性が有効です。
キャリア意識の再醸成
自身の強み・経験を棚卸しし、将来を描く機会を提供する。
学びと挑戦の機会提供
新たなスキルや業務への挑戦を通じて成長を実感できる場をつくる。
柔軟な役割・処遇設計
年齢や役職に縛られず、成果・能力に応じて役割を再設計する。
情報の透明化とマッチング精度向上
社内のキャリアパスや異動情報を可視化し、本人と組織の期待値をすり合わせる。
おわりに
ミドル社員の停滞は個人だけの問題ではなく、経営に直結する組織課題です。彼らが持つスキルや経験を最大限に発揮できる環境を整えることで、若手育成や組織変革の推進など、多方面に大きな効果をもたらします。
では、どうすればミドル世代のパフォーマンスを最大化できるのか?
その具体的なアプローチについてご紹介するセミナーを開催いたします。
セミナーのご案内
「組織の要か、足かせか ── 人事が担うミドル再生の要諦」
★ 参加特典|ミドル社員停滞要因チェックリスト
セミナーの詳細・予約はこちら