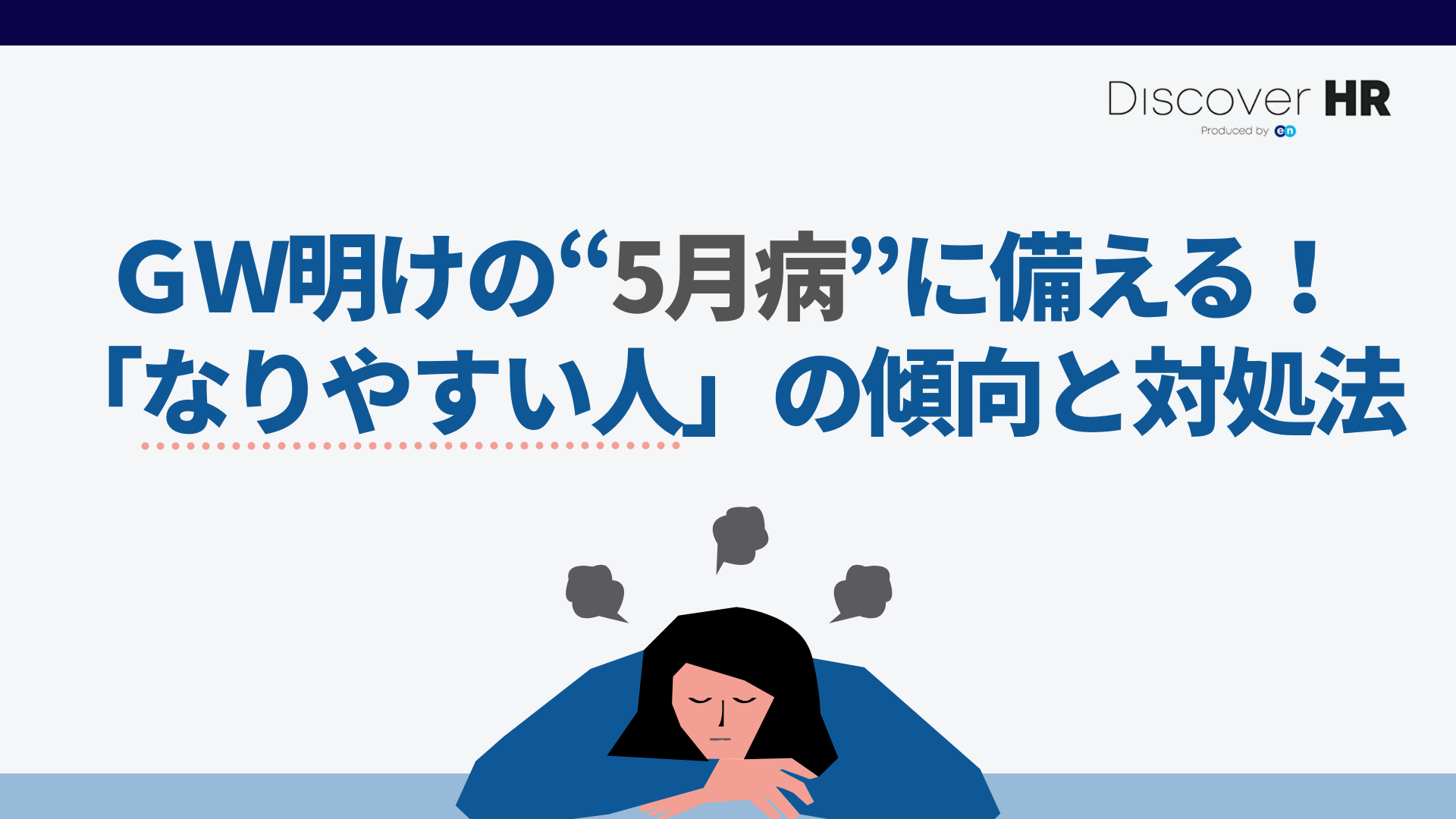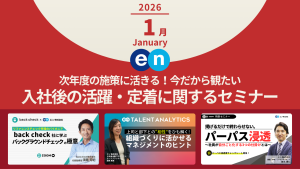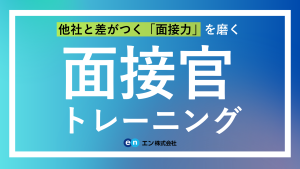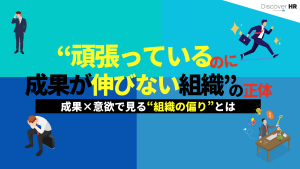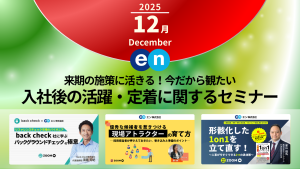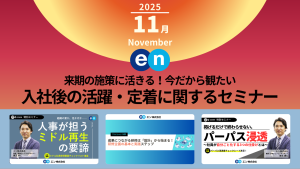5月、なんとなく元気がない…?
4月、新年度の立ち上がりもひと段落。
新入社員の受け入れも落ち着き、フレッシュで元気な若手社員が加わったことで、
職場には新しい風が吹き込んでいる頃かもしれません。
ただ――
ゴールデンウィーク明けあたりから、
「なんとなく元気がない新入社員がいる」
「異動した〇〇さんの出社が少し遅れがちになっている」
そんな勤怠の乱れや、上司からのちょっとした声が、人事の耳に届くことがあります。
この時期に増えるのが、いわゆる「5月病」です。
新年度の慌ただしさを乗り越えて、ようやくひと息…と思いきや、
連休明けを境に、心身の不調や無気力感が現れることがあります。
特に新入社員や、異動・昇進など環境の変化を経験した社員に
起こりやすい傾向があると言われています。
では、どんな人がなりやすく、
また人事・上司としてどのような対応ができるのでしょうか。
どんな人がなりやすい?
「5月病」になりやすいのは、どんな人?
対人ストレスを感じやすいタイプ
人付き合いや職場内のコミュニケーションに気を遣いやすく、
些細な人間関係の摩擦も心の負担となりやすい傾向があります。
特に、新しいチームに配属された際などは注意が必要です。
プレッシャーに敏感なタイプ
責任感が強く頑張り屋な一方で、仕事の負荷や周囲からの期待に
プレッシャーを感じやすい傾向があります。
ハイペースで駆け抜けた4月の反動が、連休明けに一気に押し寄せることも。
環境の変化に適応するのに時間がかかるタイプ
新しい業務や人間関係への順応にストレスを感じやすく、
環境が変わることで内面的な負担が高まりがちです。
理想と現実のギャップに敏感な場合、期待外れ感から
モチベーションが低下するケースも。
評価や評判への意識が強いタイプ
「迷惑をかけたくない」「失敗したくない」という気持ちが強く、
自分の感情を抑えて頑張りすぎてしまうことがあります。
周囲に相談することが難しく、1人で抱え込みやすい特徴があります。
まじめで完璧主義なタイプ
責任感が強く、周囲の期待に応えようと努力しすぎてしまうタイプ。
最初の1か月間、フルスロットルで頑張った反動で、
ゴールデンウィーク明けにエネルギーが切れてしまうことも。
では、逆に「5月病」になりづらいのは、どんな人でしょうか。
「5月病」になりづらいのは、どんな人?
ストレス発散の習慣を持っている:運動、趣味、睡眠などで切り替えられる
相談できる相手がいる:同期や上司と話せる環境がある
小さな達成感を積み重ねている:仕事に前向きな手応えを感じている
これらは、「コーピング(対処行動)※」と呼ばれるストレスとの付き合い方の差にも関係しています。
※ストレスや困難な状況に対処するための行動や心理的な対処法のこと
人事・上司ができる「コーピング支援」とは?
では、連休明けの時期に人事や上司は何ができるのでしょうか。
ポイントは「早めの気づき」と「ちょっとした声かけ」、そして“自分なりのコーピング”に気づかせる支援です。
ゴールデンウィーク前の一言
「ここまで頑張った分、休み明けすぐにペースが戻らなくても大丈夫。
焦らず、目の前のことから始めていきましょうね!」など、
“調子が落ちても大丈夫”という空気をあらかじめつくっておく。
休み明けの“ゆるスタート”
朝礼で軽く体を動かす、ミーティング前に雑談の時間をを少し長めにとるなど、
緩やかな仕事再開を意識。少しずつギアを上げていく。
上司との1on1や面談での“ふり返りタイム”
「休みはどうだった?」と気軽な会話から変化の兆しをキャッチ。
最近ハマっていることや、気分転換の方法などをさりげなく聞くことで、
その人なりの“コーピング(対処法)”に気づくきっかけにもなります。
休み明けは忙しいとは思いますが、10分でもよいのでコミュニケーションを取ることを心がけましょう。
特に、気になる社員とは人事側からも“意図的に接点を”
事前面談や研修アンケート等で気になっていた社員とは、意識的に会話の機会を。
ストレス発散の方法をさりげなく共有しあうなど、
“自分に合ったコーピング”を考えるヒントを与えることも大切です。
※適性検査の結果も参考になります。
「なんとなく元気がない」へのアンテナを
5月病は、誰にでも起こりうるもの。
だからこそ、アンテナを少し高くして「声をかける」「話を聴く」「寄り添う」ことで、
大きなトラブルの芽を早めに摘むことができます。
個々の状態に寄り添ったサポートが、人材の活躍・定着につながります。
エンでご支援できること
エンでは、採用選考の見極めだけではなく、入社後にストレスを感じやすいポイントも可視化できる適性検査『Talent Analytics(タレントアナリティクス)』を提供しています。1987年から約40年の歴史を持ち、導入企業数は21,000社を突破。ご興味があればぜひ一度無料トライアルをお申込みください。